 šĽäŚĻīÁĒüŤ™ē100ŚĻī„āíŤŅé„Āą„Āü„ÄĀ20šłĖÁīÄ„ĀģŚĀČŚ§ß„Ā™„āčšĹúśõ≤Śģ∂ „ÉĒ„ā®„Éľ„Éę„ÉĽ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„Äā2009ŚĻī„Āę„ĀĮ„ÄĆšļ¨ťÉĹŤ≥ě„Äć„ā팏óŤ≥ě„Āó„ÄĀ„Āď„Āďšļ¨ťÉĹ„ā≥„É≥„āĶ„Éľ„Éą„Éõ„Éľ„Éę„Āߌž„ĀģšĹúŚďĀ„ĀĆśľĒŚ•Ź„Āē„āĆ„āč„Ā™„Ā©„ÄĀšļ¨ťÉĹ„Ā®„āāÁłĀ„Āģś∑Ī„ĀĄšļļÁČ©„Āß„Āô„Äā
šĽäŚĻīÁĒüŤ™ē100ŚĻī„āíŤŅé„Āą„Āü„ÄĀ20šłĖÁīÄ„ĀģŚĀČŚ§ß„Ā™„āčšĹúśõ≤Śģ∂ „ÉĒ„ā®„Éľ„Éę„ÉĽ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„Äā2009ŚĻī„Āę„ĀĮ„ÄĆšļ¨ťÉĹŤ≥ě„Äć„ā팏óŤ≥ě„Āó„ÄĀ„Āď„Āďšļ¨ťÉĹ„ā≥„É≥„āĶ„Éľ„Éą„Éõ„Éľ„Éę„Āߌž„ĀģšĹúŚďĀ„ĀĆśľĒŚ•Ź„Āē„āĆ„āč„Ā™„Ā©„ÄĀšļ¨ťÉĹ„Ā®„āāÁłĀ„Āģś∑Ī„ĀĄšļļÁČ©„Āß„Āô„Äā
„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀģÁĒüŤ™ē100ŚĻī„ā퍮ėŚŅĶ„Āó„Ā¶„ÄĀ„ā™„É™„āł„Éä„ÉęšľĀÁĒĽ„ÄĆ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„Āł„Āģ„ā™„Éě„Éľ„āł„É•„Äć„āíťĖčŚā¨„Āó„Āĺ„ĀôÔľą11śúą8śó•ÔľČ„Äā
śú¨ŚÖ¨śľĒ„ĀģŚáļśľĒŤÄÖ„Āß„Āā„āä„ÄĀ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀĆŤ®≠Áęč„Āó„ĀüšłĖÁēĆŚĪąśĆá„Āģ„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„ÄĆ„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ÉÜ„Éę„ā≥„É≥„āŅ„É≥„ÉĚ„É©„É≥„Äć„ĀģŚįāŚĪě„ÉĒ„āĘ„Éč„āĻ„Éą„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀÁīĄ20ŚĻī„āā„ĀģťĖď„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„Ā®śīĽŚčē„āíŚÖĪ„Āę„Āó„ĀüśįłťáéŤčĪś®Ļ„Āē„āď„Āę„ā§„É≥„āŅ„Éď„É•„Éľ„ā퍰ƄĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚÜÖŚģĻ„āíŚČćÁ∑®„ÉĽŚĺĆÁ∑®„Āꌹ܄ĀĎ„Ā¶„ĀäŚĪä„ĀĎ„Āó„Āĺ„Āô„Äā
„Äź„ā§„É≥„āŅ„Éď„É•„ÉľŚČćÁ∑®Ôľö„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĎ
‚Äē‚Äē‚Äē„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀĮšĹúśõ≤„Ā†„ĀĎ„Āß„Ā™„ĀŹ„ÄĀśĆᜏģ„āĄŤĎóŤŅį„Ā™„Ā©„ÄĀťü≥ś•ĹŚģ∂„Ā®„Āó„Ā¶„Āģ„Āē„Āĺ„ĀĖ„Āĺ„Ā™ŚßŅ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀśįłťáé„Āē„āď„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀĮ„Ā©„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ťü≥ś•ĹŚģ∂„Āß„Āô„ĀčÔľü
ÁßĀ„Āę„Ā®„Ā£„Ā¶„ĀĮśĆᜏģŤÄÖ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āą„āä„āā„āÄ„Āó„āć„ÄĀšĹúśõ≤Śģ∂„Ā®„Āó„Ā¶„Āģ„ā§„É°„Éľ„āł„ĀģśĖĻ„ĀĆŚľ∑„Āč„Ā£„Āü„Āß„Āô„Ā≠„Äā„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āģ„āā„ÄĀÁßĀ„ĀĮÁīĒÁ≤č„Āę„ā™„Éľ„āĪ„āĻ„Éą„É©„āą„āä„āā„ÉĒ„āĘ„Éé„ĀĆŚ•Ĺ„Āć„Ā†„Ā£„Āü„Āģ„Āß„ÄĀ„ÉĒ„āĘ„Éé„Āģśõ≤„āíŤĀī„ĀŹśĖĻ„ĀĆŚ§ö„ĀŹ„ÄĀśĆᜏģŤÄÖ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀģŚĹľ„ĀģŚßŅ„āí„Āā„Āĺ„ā䜥ŹŤ≠ė„Āó„Āü„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āõ„āď„Āß„Āó„Āü„Äā
Śģüťöõ„ÄĀÁßĀ„ĀĆ„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ÉÜ„Éę„ā≥„É≥„āŅ„É≥„ÉĚ„É©„É≥Ôľä„ĀęŚÖ•„Ā£„Ā¶„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„Ā®šłÄÁ∑í„Āꚼēšļč„āí„Āó„Āüťöõ„ÄĀ„ÄĆť†ľ„Āĺ„āĆ„Āü„āČśĆᜏģ„āí„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ĀĎ„āĆ„Ā©„ÄĀŤá™ŚąÜ„ĀĮšĹúśõ≤Śģ∂„Ā†„Ā®śÄĚ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāŤá™ŚąÜ„Āč„āČÁéáŚÖą„Āó„Ā¶„āĄ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Āģ„ĀĮšĹúśõ≤„Ā†„Äć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āą„ĀÜ„Ā™„Āď„Ā®„ā퍮ĄĀ£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āü„Ā†„ÄĀśúÄÁĶāÁöĄ„Āę„ĀĮśĆᜏģ„ĀģšĽēšļč„ĀģśĖĻ„ĀĆ„Āö„ĀĄ„Ā∂„āö„Āč„Ā£„Āüśįó„ĀĆ„Āó„Āĺ„Āô„Äā
Ôľä„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ÉÜ„Éę„ā≥„É≥„āŅ„É≥„ÉĚ„É©„É≥
1976ŚĻī„Āę„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀĆŤ®≠Áęč„Āó„Āü„ÄĀšłĖÁēĆśúÄťęėŚ≥į„ĀģÁŹĺšĽ£ťü≥ś•Ĺ„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„Äā
„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„ĀģśīĽŚčē„āĄŚĹďśôā„Āģ„ā®„ÉĒ„āĹ„Éľ„ÉČ„Ā™„Ā©„ĀĮ„ÄĀ2018ŚĻī„ĀęťĖčŚā¨„Āó„Āü„ÄĆšļ¨ťÉĹ„ā≥„É≥„āĶ„Éľ„Éą„Éõ„Éľ„Éę„Āģ„āĻ„Éö„ā∑„É£„Éę„ÉĽ„ā∑„É™„Éľ„āļ„ÄéŚÖČ„Ā®ŤČ≤ŚĹ©„ĀģšĹúśõ≤Śģ∂ „āĮ„É≠„Éľ„ÉČ„ÉĽ„ÉČ„Éď„É•„ÉÉ„ā∑„Éľ„ÄŹ„Äć„ĀģśįłťáéŤčĪś®ĻśįŹ„ā§„É≥„āŅ„Éď„É•„Éľ„āí„ĀĒŤ¶ß„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā
‚Äē‚Äē‚Äēśįłťáé„Āē„āď„ĀĆśĄü„Āė„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āü„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļŚÉŹ„Ā®„ÄĀ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀĆśÄĚ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀüŤá™Ťļę„ĀģŚßŅ„ĀĮšłÄŤáī„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„Āß„Āô„Ā≠„Äā
„ĀĚ„ĀÜ„Āß„Āô„Ā≠„Äā„āā„Ā£„Ā®śÄĖ„ĀĄšļļ„Ā†„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ā§„É°„Éľ„āł„ĀĆ„Āā„Ā£„Āü„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĮšļąśÉ≥„Āꌏć„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Ā≠„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀśúČŚźćšļļ„Ā™„Āģ„Āę„ÄĀ„āĶ„ā§„É≥„āíśĪā„āĀ„āČ„āĆ„Āü„Ā®„Āć„ĀĮŚČ≤„Ā®śįóŤĽĹ„ĀęŚŅú„Āė„Ā¶Ť©Ī„āā„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„ÄāŤ°ó„āíś≠©„ĀĄ„Ā¶„ĀĄ„Ā¶„āāŚĹľ„Āęśįó„ĀĆ„Ā§„Āč„ĀöťÄö„āäťĀé„Āé„Ā¶„ĀĄ„āčšļļ„āāÁĶźśßč„ĀĄ„Āü„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„ĀÜ„ĀĄ„ĀܝɮŚąÜ„Āß„ĀĮ„āĻ„āŅ„ÉľśĄŹŤ≠ė„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āā„Āģ„ĀĮ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„āą„ĀÜ„Āꜥü„Āė„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
‚Äē‚Äē‚ÄēšĽä„ĀģŤ©Ī„Ā†„ĀĎ„Āß„āā„ÄĀ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀęŚĮĺ„Āô„āč„ā§„É°„Éľ„āł„ĀĆ„Āö„ĀĄ„Ā∂„āȄāŹ„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā
„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ÉÜ„Éę„ā≥„É≥„āŅ„É≥„ÉĚ„É©„É≥„ĀĮ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļŤá™Ťļę„ĀĆšĹú„Ā£„Āü„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„Āß„Āô„Āģ„Āß„ÄĀšĽĖ„Āģ„ā™„Éľ„āĪ„āĻ„Éą„É©„āą„āä„āā„ÄĀ„Éõ„Éľ„Ɇ„ĀŅ„Āü„ĀĄ„ĀęśÄĚ„Ā£„Ā¶„ĀŹ„Ā†„Āē„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Ā≠„Äā„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ÉÜ„Éę„ā≥„É≥„āŅ„É≥„ÉĚ„É©„É≥„Āģ„É°„É≥„Éź„Éľ„Ā®śé•„Āô„āč„Ā®„Āć„ĀĮ„ÄĀŚĹľ„āā„Āä„ĀĚ„āČ„ĀŹšĽĖ„Āģ„ā™„āĪ„Āģšļļ„Āü„Ā°„Ā®śé•„Āô„āč„āą„āä„āā„É™„É©„ÉÉ„āĮ„āĻ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āģ„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Āč„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
‚Äē‚Äē‚Äē„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ÉÜ„Éę„ā≥„É≥„āŅ„É≥„ÉĚ„É©„É≥„Āß„ÄĀśįłťáé„Āē„āď„ĀĮŚįāŚĪě„ÉĒ„āĘ„Éč„āĻ„Éą„Ā®„Āó„Ā¶20ŚĻī„ĀĽ„Ā©„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„Ā®šłÄÁ∑í„ĀęśīĽŚčē„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀŚćįŤĪ°„Āęśģč„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āčŚáļśĚ•šļč„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āô„ĀčÔľü

ŚĹľ„ĀģšĹúśõ≤„Āģ„āĻ„āŅ„ā§„Éę„Āß„āā„Āā„āč„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀśô©ŚĻī„ĀĮ„ÉĮ„Éľ„āĮ„ÉĽ„ā§„É≥„ÉĽ„Éó„É≠„āį„ɨ„āĻ**„Āģ„āĻ„āŅ„ā§„Éę„ĀßšĹúśõ≤„āí„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„ÄāŚłł„ĀęšĹúŚďĀ„ĀĆťÄ≤Ť°ĆŚĹĘ„Āß„Āā„āä„ÄĀ‚Äú„ĀĄ„Āĺ„Āģ„Ā®„Āď„āć„Āď„ĀģŚĹĘ„Āß„Ā®„Ā©„āĀ„Ā¶„ĀĄ„āč„ĀĎ„āĆ„Ā©„ÄĀšĽäŚĺĆŤ¶čÁõī„Āó„Ā¶śįóśĆĀ„Ā°„ĀĆŚ§Č„āŹ„Ā£„Āü„āČŚ§ČŚĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„āą‚ÄĚ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āą„ĀÜ„Ā™„āĻ„āŅ„ā§„Éę„Āß„Āô„Äā
„Āä„āā„Āó„āć„ĀĄŚáļśĚ•šļč„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀ3ŚŹį„Āģ„ÉĒ„āĘ„Éé„Ā®3ŚŹį„Āģ„ÉŹ„Éľ„Éó„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶3„Ā§„ĀģťćĶÁõ§śČďś•ĹŚô®„Āģ„Āü„āĀ„ĀģšĹúŚďĀ„Ää„ā∑„É•„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ā∑„Éľ„āļ„Äč„Āę„Āĺ„Ā§„āŹ„ā荩Ī„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āô„Äā„Āď„ĀģšĹúŚďĀ„ĀģŚÖÉ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Āģ„ĀĮ„Ää„āĘ„É≥„ā∑„Éľ„āļ„Äč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÉĒ„āĘ„Éé„ÉĽ„āĹ„É≠„ĀģšĹúŚďĀ„Āß„ÄĀ„ā≥„É≥„āĮ„Éľ„Éę„ĀģŤ™≤ť°Ćśõ≤„Ā®„Āó„Ā¶śõł„Āč„āĆ„Āü„āā„Āģ„Āß„Āô„Äā„Ää„āĘ„É≥„ā∑„Éľ„āļ„Äč„ĀģśģĶťöé„Āß„ĀĮ5ŚąÜ„ĀŹ„āČ„ĀĄ„Āģśõ≤„Ā†„Ā£„Āü„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀśēįŚĻīŚĺĆ„ÄĀ„Ää„ā∑„É•„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ā∑„Éľ„āļ„Äč„Āę„Ā™„Ā£„Āüśôā„Āę„ĀĮ30ŚąÜ„ĀŹ„āČ„ĀĄ„Āģťē∑„Āē„Āģśõ≤„Āę„Ā™„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„Āó„Āü„āČšĽäŚļ¶„ĀĮ„Ää„ā∑„É•„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ā∑„Éľ„āļ„Äč„ĀęŤß¶Áôļ„Āē„āĆ„Āü„Āģ„Ā茹܄Āč„āä„Āĺ„Āõ„āď„ĀĆ„ÄĀ„Ää„āĘ„É≥„ā∑„Éľ„āļ„Äč„Āģśõ≤„Āģťē∑„Āē„ĀĆ10ŚąÜ„ĀŹ„āČ„ĀĄ„ĀęŚĘó„Āą„Āü„āď„Āß„Āô„Ā≠„Äā„ĀĚ„Āó„Āü„āČ„Āĺ„Āü„Ää„ā∑„É•„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ā∑„Éľ„āļ„Äč„ĀģśĖĻ„āā„Āē„āČ„ĀꌧȌĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā£„Ā¶‚Ķ„Äā
„Ää„āĘ„É≥„ā∑„Éľ„āļ„Äč„Ā®„Ää„ā∑„É•„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ā∑„Éľ„āļ„Äč„ĀęťĖĘ„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀšłÄÁē™ŚąĚ„āĀ„Āģ„Éź„Éľ„āł„Éß„É≥„Āč„āČŚĪÖŚźą„āŹ„Āõ„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āģ„Āß„ÄĀśõ≤„ĀĆ„Ā©„āď„Ā©„āďśĖį„Āó„ĀŹŚ§Č„āŹ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀŹŚ†īťĚĘ„ĀęÁęč„Ā°šľö„Āą„Āü„Āď„Ā®„ĀĮ„ÄĀ„Ā®„Ā¶„āāŤ≤īťáć„Ā™ÁĶĆť®ď„Āß„Āó„Āü„Äā„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„Ā®ŚÖĪ„Āę„ĀĄ„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ÁĶĆť®ď„ĀĮ„Āß„Āć„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Ā≠„Äā
ÔľäÔľä„ÉĮ„Éľ„āĮ„ÉĽ„ā§„É≥„ÉĽ„Éó„É≠„āį„ɨ„āĻ
ťÄ≤Ť°Ćšł≠„ĀģšĹúŚďĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜśĄŹŚĎ≥„ÄāŚČĶšĹú„ĀģťĀéÁ®č„āíŚÖ¨ťĖč„Āó„Ā¶„ÄĀŤĀīŤ°Ü„ĀģŚŹćŚŅú„ā팏āŤÄÉ„Āę„Āó„Ā™„ĀĆ„āČšĹúŚďĀ„āíŚČĶ„āäšłä„Āí„Ā¶„ĀĄ„ĀŹśČčś≥ē„Äā
‚Äē‚Äē‚ÄēšĹúśõ≤Śģ∂„ĀģśČč„Āę„āą„āäśõ≤„ĀĆŚ§ČŚĆĖ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āć„ÄĀ„ĀĚ„Āó„Ā¶„ĀĚ„ĀģťĀéÁ®č„ÉĽŚ§ČŚĆĖ„ā퍶čŤĀī„Āć„Āß„Āć„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁĶĆť®ď„ĀĮ„ÄĀÁŹĺšĽ£ťü≥ś•Ĺ„Ā™„āČ„Āß„ĀĮ„Āß„Āô„Ā≠„Äā
śľĒŚ•ŹŚģ∂„ĀĆŚźĆ„ĀėšĹúŚďĀ„āí10ŚĻīŚĺĆ„ÄĀ20ŚĻīŚĺĆ„ĀęśľĒŚ•Ź„Āó„Āüťöõ„ĀęŤß£ťáą„ĀĆŚ§Č„āŹ„āč„Āģ„Ā®ŚźĆ„Āė„āą„ĀÜ„Āę„ÄĀšĹúśõ≤Śģ∂„ĀĆšĹúŚďĀ„ā팧ȄĀą„Ā¶„ĀĄ„ĀŹ„Āģ„ĀĮŚĹďÁĄ∂„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āą„ĀÜ„Ā™„Āď„Ā®„āā„ÄĀ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀĮŤ®Ä„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Ā≠„ÄāŤÄÉ„ĀąśĖĻ„āāŚ§Č„āŹ„āč„āą„ÄĀ„Ā£„Ā¶„Äā
‚Äē‚Äē‚Äē„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀģšĹúŚďĀ„āíśú¨šļļ„Ā®ŚÖĪ„ĀęśľĒŚ•Ź„Āô„āč„Āď„Ā®„āā„Āā„Ā£„Āü„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„ĀĆ„ÄĀšĹúŚďĀ„āĄśľĒŚ•ŹśĖĻś≥ē„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ť®ÄŤĎČ„āíšļ§„āŹ„Āô„Āď„Ā®„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„ĀčÔľü
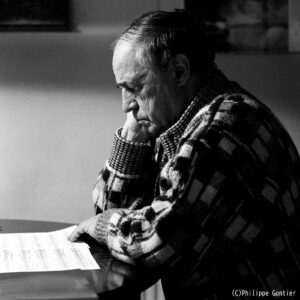
„āĹ„É≠„ĀģšĹúŚďĀ„ā팾ĺ„ĀŹ„Ā®„Āć„Āę„ĀĮÁõīśé•ŤĀī„ĀĄ„Ā¶„āā„āČ„ĀĄ„ÄĀ„āĘ„ÉČ„Éź„ā§„āĻ„āí„āā„āČ„Ā£„Āü„āä„Āó„Āĺ„Āó„Āü„Ā≠„Äā„āĹ„É≠„ĀģšĹúŚďĀ„Āęťôź„āČ„Āö„ÄĀ‚ÄúŚčē„Āć„ĀĆŚ§ßŚąá‚ÄĚ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļÁč¨ÁČĻ„Āģťü≥ś•Ĺ„ĀģŤÄÉ„ĀąśĖĻ„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„ÄāťĚĘÁôĹ„Āč„Ā£„Āü„Āģ„ĀĮ„ÄĀšĺč„Āą„Āįśó©„ĀŹŚľĺ„ĀŹ„āą„ĀÜ„Ā™„ÉÜ„āĮ„Éč„ÉÉ„āĮÁöĄ„Āꌧߌ§Č„Ā™„Ā®„Āď„āć„ĀĆ„Āā„Ā£„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„āā„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„ĀĆ„Āö„Ā£„Ā®ŚźĆ„Āė„É™„āļ„Ɇ„ĀßÁ∂ö„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„āď„Āß„Āô„Ā≠„ÄāŚŅÖ„Āö„Ā©„Āď„Āč„Āß„ĀĚ„Āģ„É™„āļ„Ɇ„āíŚī©„Āô„Ā®„Āď„āć„ĀĆ„Āā„āč„āď„Āß„Āô„ÄāŚ§ßŚ§Č„Āߍ§áťõĎ„Ā™„É™„āļ„Ɇ„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„Āö„Ā£„Ā®„ĀĚ„āĆ„āíÁĻį„āäŤŅĒ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®ŚģöÁĚÄ„ĀóŚģČŚģö„Āó„Āü„āā„Āģ„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„Āó„Āĺ„ĀÜ„Āģ„Āß„Āô„ĀĆ„ÄĀ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀĮ„ĀĚ„āĆ„ĀĆŚęĆ„Āß„ÄĀŚłł„ĀęŚģČŚģö„Āó„Āü„É™„āļ„Ɇ„āíŚī©„Āô„āą„ĀÜ„Ā™Śčē„Āć„āíŚÖ•„āĆ„Ā¶„ĀŹ„āč„āď„Āß„Āô„āą„Ā≠„Äā„ÄĆť≠ö„ĀĆśĪ†„Āßś≥≥„ĀĄ„Āß„ĀĄ„āč„Ā®„Āć„ÄĀ„āÜ„Ā£„ĀŹ„āäś≥≥„ĀĄ„Āß„ĀĄ„āč„Ā®śÄĚ„Ā£„Āü„āȜĕ„Āę„āĻ„ÉÉ„Ā®Śčē„ĀŹ„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āč„Äā„ĀĚ„ĀÜ„ĀĄ„ĀÜ„ā§„É°„Éľ„āł„Ā†„āą„Äā„Äć„Ā®„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀĆšĺč„Āą„Āü„Āď„Ā®„ĀĆ„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äāśó•śú¨ÁöĄ„Ā†„Ā™„Ā®śĄü„Āė„Āĺ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ„ĀĚ„ĀÜ„ĀĄ„ĀÜśôāťĖď„āĄŚĎľŚźł„ĀģŤÄÉ„ĀąśĖĻ„ÄĀťü≥ś•Ĺ„Āģ„Ā®„āČ„ĀąśĖĻ„ĀĮ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļśú¨šļļ„Ā†„Āč„āČŤ™¨śėé„Āß„Āć„āč„Āď„Ā®„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„ÄĀ„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļšĽ•Ś§Ė„Āę„ĀĮŚáļ„Āõ„Ā™„ĀĄ„ā§„É°„Éľ„āł„Ā™„Āģ„Ā†„āć„ĀÜ„Ā™„Ā®śÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„ĀĚ„ĀÜ„ĀĄ„Ā£„ĀüŚáļśĚ•šļč„ĀĮšĽĖ„Āę„āā„ĀĄ„āć„ĀĄ„āć„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„Ā®šłÄÁ∑í„ĀęŚĹľ„ĀģšĹúŚďĀ„āíśľĒŚ•Ź„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„ÄĀ„āą„āä„ÉĖ„Éľ„ɨ„Éľ„āļ„ĀģŤÄÉ„ĀąśĖĻ„āíśēô„Āą„Ā¶„āā„āČ„Ā£„Āü„āą„ĀÜ„ĀęśÄĚ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā
‚Äē‚Äē‚Äē„Éó„É©„ā§„Éô„Éľ„Éą„Āß„ĀģŤ¶™šļ§„ĀĮ„Āā„āä„Āĺ„Āó„Āü„ĀčÔľü
„Éó„É©„ā§„Éô„Éľ„Éą„Āß„ĀĮ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āß„Āô„Ā≠„Äā„Āü„Ā†„ÄĀŚĹľ„ĀĮ„Āď„āĆ„Āĺ„ĀßšĹēšļļ„Āč„ĀĄ„ĀüÔľą„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ÉÜ„Éę„ā≥„É≥„āŅ„É≥„ÉĚ„É©„É≥„ĀģԾȝü≥ś•ĹÁõ£ÁĚ£„ĀģŤ™į„āą„āä„āā„ÄĀÁßĀ„Āü„Ā°„É°„É≥„Éź„Éľ„Āģ„ĀĚ„Āį„Āę„ĀĄ„Ā¶„ĀŹ„āĆ„āčśĖĻ„Āß„Āó„Āü„Äāšĺč„Āą„ĀįŚźĆ„Āė„ā≥„É≥„āĶ„Éľ„Éą„Āß„āĹ„É≠„āĄ„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„Ā™„Ā©Ťá™ŚąÜ„ĀĆśĆᜏģ„āí„Āó„Ā™„ĀĄśõ≤„ĀĆ„Āā„Ā£„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„āā„ÄĀŚŅÖ„ĀöśľĒŚ•Ź„āíŤĀī„ĀĄ„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„Āĺ„ĀüŚĹľ„ĀĆ„ÉĎ„É™„Āę„ĀĄ„āč„Ā®„Āć„Āę„āĘ„É≥„āĶ„É≥„ÉĖ„Éę„ÉĽ„āĘ„É≥„ÉÜ„Éę„ā≥„É≥„āŅ„É≥„ÉĚ„É©„É≥„Āģ„ā≥„É≥„āĶ„Éľ„Éą„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„ÄĀŚŅÖ„ĀöŤĀī„Āć„ĀęśĚ•„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀÜ„ĀĄ„ĀܝɮŚąÜ„Āß„ÄĀŚłł„Āę„ĀĚ„Āį„Āę„ĀĄ„Ā¶„ĀŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄĀ„Ā®„ĀĄ„ĀÜśĄü„Āė„Āß„Āó„Āü„Ā≠„Äā
‚Äē‚Äē‚Äē„ā™„Éľ„āĪ„āĻ„Éą„É©„Ā®śĆᜏģŤÄÖ„Ā®„ĀĄ„ĀÜťĖĘšŅā„āą„āä„āā„ÄĀšĽ≤ťĖď„Ā®„ĀĄ„ĀÜťĖĘšŅāśÄß„Āß„Āô„Ā≠„ÄāŚĺĆÁ∑®„Āß„ĀĮšĽäŚõě„Āģ„ā≥„É≥„āĶ„Éľ„Éą„Āģ„Éó„É≠„āį„É©„Ɇ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„Ā䍩Ī„āíšľļ„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā„Ā©„ĀÜ„Āě„Āäś•Ĺ„Āó„ĀŅ„ĀęÔľĀ
Ôľą2025ŚĻī4śúąŚ§ßťė™„Āę„Ā¶„ÄÄšļčś•≠šľĀÁĒĽŤ™≤„ÄÄŚĪĪŚÖÉťļĽÁĺéÔľČ
