このたび、京都コンサートホールが開館30周年を記念して、京都ゆかりの著者16名によるエッセイ本『超楽器』を世界思想社より刊行いたしました。編者をつとめた、京都コンサートホール鷲田清一館長と、高野裕子プロデューサーに本書についてお聞きしました。
まだお手に取られていない方は、ご購入のきっかけに、お手に取ってくださった方は、刊行の裏話として、ぜひ最後までお読みください。

―――「超楽器」刊行にあたって、いまの率直な思いをお聞かせください。
鷲田館長:開館から30年経って、最近の京都コンサートホールはチケットが完売になるなど、たくさんのお客様にお越しいただいています。これまで、本当に多くの人に支えられてきました。今回刊行した『超楽器』は、そんなホールを支えてきてくれた方が手に取って、喜んでくれる本にしたかった。読み物として、手に取りやすく、読んで面白い本にしたかったんですよね。

いま、京都コンサートホールは“クラシック音楽の殿堂”と呼ばれていますが、「クラシック音楽」という言葉の定義って難しいですよね。たとえば、現代音楽も「クラシック音楽」として一括りにされていますが、そもそも現代音楽にはジャズや民族音楽なども入っており、その境界線は曖昧です。元来、音楽にはグラデーションのように、先鋭的なものから、鼻歌や盆踊りといった生活に密接に関わっているものなどが多様にあります。それに関わる人たちもプロフェッショナルからアマチュアまで、色々な人がいますね。歌う場所も、音楽ホールからカラオケまである。クラシックに限らず、音楽って境界線を引きにくいものなのです。言ってみれば、どんな人でも関わることのできるものなのです。だから、この『超楽器』の執筆者を決める時は、クラシックの専門家だけではなく、山極壽一さんのようにジャングルのゴリラの世界から金剛永謹さんの邦楽の世界まで、意外なジャンルまで拡げて、読み手がどこからでも入れるように心がけました。
―――色々な方が色々な視点から音楽にアプローチして書かれていて、著者によっては、音楽へのネガティブな思いをスタートに書かれている方もいらっしゃる。視点や入り口は各々さまざまなのに、どのお話も結局読み終わると、「音楽っていいよね」に帰結する内容になっていますよね。
鷲田館長:著者の中には、最初は音楽が「嫌い」だったのに、あることをきっかけにぐっと「好き」に寄ってきた人もいる。本書の中では語られていないけれども、岡田暁生さんのようにピュアな、コアなクラシック音楽ファンが、いつの間にかジャズに夢中になっていたりすることもある。同じ音楽の中でも色々なジャンルや視点で「行ったり来たり」できるところが音楽の面白さであり、難しさでもあるのでしょうね。
―――著者皆さんプロフェッショナルなのに、「こう」という決めつけがない。その面白さがこの本の中に詰まっていることが素晴らしいと感じました。
鷲田館長:さっき「行ったり来たり」と言いましたが、それが顕著に現れているページがあります。文末の著者紹介のページです。みなさんに「好きな曲」をお尋ねしたのですが、クラシック系の人はポピュラーやフォークソングを挙げているのに対し、音楽家でない人たちはクラシック系の曲を挙げているのが面白いですよね。
高野プロデューサー:鷲田館長は・・・(ページをめくる)「好きな曲」はフォーレのレクイエムで、「好きな楽器」はエレクトリック・ギターだそうで(笑)。
鷲田館長:ちょっと反抗してみました(笑)。
高野プロデューサー:そこが鷲田館長らしいなぁと。
鷲田館長:みなさんそういう落差ってありますよね。
高野プロデューサー:ぜひみなさんにも最後の著者紹介まで楽しんでいただきたいですね。
鷲田館長:こうやって著者の方々をあらためて見てみると、色々なジャンルの方が書いてくださいましたね。きっと手に取るファンの方々も様々な方がいらっしゃるでしょうね。
高野プロデューサー:この本を通じて、きっと色んなジャンルのファンが交差してくれるでしょうね。
―――ありがとうございます!
京都コンサートホールに限らず、こういった音楽ホールというものが、この先の未来でどういった形なることが望ましいか、音楽ホールに対する想いや夢があればお聞かせください
鷲田館長:「施設」として一番幸福なことは、それを使う人とその周りに暮らしている人々がハッピーであること。「ああ、ここにあってくれてよかった」と思ってもらえること。ここを訪れる人、地域の人にとって、この施設があることでどれだけの満足感があるかが大切だと思っています。そういう施設になるためには、良いコンサートや企画が必要です。音楽は聴くだけではなく、色々な楽しみ方があります。例えば聴くだけではなく、踊ったり、雰囲気を感じたり。そういった色々な楽しみ方を、ここ京都コンサートホールの様々な場所を使いながら提供していくことができればいいなと思います。僕の夢は、世界中の人が「京都コンサートホールっていうすごいホールがある」と認識してくださると同時に、地元の人々から非常に愛される存在にホールがなってくれることです。
―――私事なのですが、幼い頃から北山地域に近い場所に暮らしていて、働く前から、ホールに足を運んでいました。思えば30年ずっと当たり前にホールがここにありました。それは特別で有難いことなのだとあらためて大人になって思います。
鷲田館長:僕もそう思います。優秀な建物は、意味がわからなくても、わけのわからない子どもにとっても、そこにあると心地の良い存在だと思います。そういえばこれまであまり見かけたことがないけど、京都コンサートホールの敷地内でもっと子供たちが遊んでいても良いなと思っています。朝、子供たちが遊んでいて、少し悪さをして、守衛さんが出てきて「こらー!!!」と怒鳴っていたりね。まるでお寺みたいだよね。
お寺は昔から子供が遊ぶ場所で、和尚さんがコラ!と怒鳴ると子供たちが散り散りに逃げて行きます。京都コンサートホールもそんな場所であったらいいとおもいます。
―――でも一方では、一流のアーティストが来て演奏しているということですね。
鷲田館長:自分たちが遊んでいるところに、なんか綺麗な着飾った人が沢山来ている。それを見て子供たちが「何やってるんやろ?」と興味を持つ。僕はそういう景色が好きです。そういう施設にならないといけないですね。
高野プロデューサー:京都コンサートホールをはじめ、ご近所さんの京都府立植物園や京都府立大学、京都学・歴彩館も含めてこの辺り一帯が京都を代表する文化ゾーンになったらいいですよね。
鷲田館長:「京都の音」といったら「除夜の鐘」だけれども、「京都コンサートホールの音」ができるといいですよね。例えばクリスマスになったらクリスマスの演奏とかね。京都を訪れると、京都の色々な音が聴こえてきます。その中の一つに「京都コンサートホールの音」が入ってくるといいね。
高野プロデューサー:館長は『超楽器』の中でも書いていらっしゃいますね(ページをめくる)――川のせせらぎ、鳥のさえずり、お寺の鐘の音、部屋越しに聞こえてくる祇園の三味線の音。それに「京都コンサートホールから聞こえてくる音楽」が加わると最高ですね。
―――『超楽器』はどんな方に手に取ってもらいたいですか。
高野プロデューサー:この書籍の構想を練る時、「どんな本にしたいか」ということについて、鷲田館長と出版元である世界思想社の編集者の方と3人でああでもない、こうでもないと話し合いました。3人に共通していたのは、「クラシック音楽にこれまで縁がなかった人にも読んでほしい」という想いでした。クラシック音楽にこれまで縁がなかった方でも面白く読んでいただけるような内容に仕上がっているなと思いますし、本を読んだ後に「なんかクラシック音楽って楽しそう」「京都コンサートホールにいっぺん行ってみようかな」と思ってくださると嬉しいです。
もちろんこの本には、これまで京都コンサートホールを支えてくださったファンの方々への感謝の気持ちもたくさん詰まっています。「30年間、京都コンサートホールにお越しくださってありがとうございます」というわたしたちスタッフの気持ちがこの本を介してたくさんの方々に伝わるといいですね。
―――これから『超楽器』を手に取られる方へのメッセージをお願いします。
鷲田館長:読んだら人にプレゼントしたくなる一冊です。
高野プロデューサー:装丁もとても素敵に綺麗に作っていただきました。鷲田館長は構想の段階から「人にプレゼントしたくなるような本にしたい」とおっしゃっていましたしね。
鷲田館長:執筆者には、クラシック音楽について真正面から語るのは今回が初めてではないかと思うような方もいらっしゃる。
高野プロデューサー:本当に豪華な執筆陣で、感謝の気持でいっぱいです。色んなジャンルのプロフェッショナルが語る音楽体験が掲載されているので、本をきっかけにみなさんの特別な音楽体験についても思い起こしていただけると嬉しいです。

―――ありがとうございました!
ぜひ皆さま、実際にお手に取って、読んで、音楽を一層好きになる。京都コンサートホールに来たくなる。
そんな素敵な読書時間となりましたら幸いです。
もしよろしければ、アンコールの拍手喝采の気持ちで、ご友人へのプレゼントもご検討ください!
京都コンサートホール30周年記念エッセイ本『超楽器』は好評販売中です。
(2025年10月某日
聞き手・構成:京都コンサートホール事業企画課 日浦由美子)

 たちによる夢の競演「ブラス・スターズ in KYOTO」(11月30日)。
たちによる夢の競演「ブラス・スターズ in KYOTO」(11月30日)。 初めて作曲をしたのは、たしかピアノを初めてすぐの頃でした。ピアノ曲で、「子犬の行進」や「星のうた」といったタイトルをつけて作曲していました。幼い頃から「楽譜を書く」ことが何より好きだったみたいです。
初めて作曲をしたのは、たしかピアノを初めてすぐの頃でした。ピアノ曲で、「子犬の行進」や「星のうた」といったタイトルをつけて作曲していました。幼い頃から「楽譜を書く」ことが何より好きだったみたいです。 実は「たなばた」の作曲は高校時代にしました。私の曲には転調が繰り返し現れるので、当時高校の同級生には難しいと感じられて、よく煙たがられていましたね(笑)。だから、「たなばた」も当時演奏されることはあまりありませんでした・・・。「たなばた」が日の目を見ることになったのは大阪音楽大学2年生の時です。当時大学で吹奏楽を指導していらっしゃった先生たちの前で「たなばた」をピアノで初披露したところ気に入ってくださり、そのまま吹奏楽編成で演奏していただきました。
実は「たなばた」の作曲は高校時代にしました。私の曲には転調が繰り返し現れるので、当時高校の同級生には難しいと感じられて、よく煙たがられていましたね(笑)。だから、「たなばた」も当時演奏されることはあまりありませんでした・・・。「たなばた」が日の目を見ることになったのは大阪音楽大学2年生の時です。当時大学で吹奏楽を指導していらっしゃった先生たちの前で「たなばた」をピアノで初披露したところ気に入ってくださり、そのまま吹奏楽編成で演奏していただきました。 ラヴェルの「道化師の朝の歌」についてはとても難しい楽曲ですが、ピアノと打楽器が入ることによって色々な工夫ができるので、それがとても楽しいです。「800秒間世界一周」についてはお気づきの方もいらっしゃると思いますが、1956年にアメリカで公開された映画「80日間世界一周」にかけています。この曲では、まず日本を出発し、色んな世界の音楽を聴いてもらいながら、お客さんに世界旅行の気分を味わってもらいたいなと思っています。それぞれの楽器にフィーチャーして、色んな表現をお客様にお聴きいただけたらいいなと思っています。
ラヴェルの「道化師の朝の歌」についてはとても難しい楽曲ですが、ピアノと打楽器が入ることによって色々な工夫ができるので、それがとても楽しいです。「800秒間世界一周」についてはお気づきの方もいらっしゃると思いますが、1956年にアメリカで公開された映画「80日間世界一周」にかけています。この曲では、まず日本を出発し、色んな世界の音楽を聴いてもらいながら、お客さんに世界旅行の気分を味わってもらいたいなと思っています。それぞれの楽器にフィーチャーして、色んな表現をお客様にお聴きいただけたらいいなと思っています。
 京都には、高校1年生から30歳までいました。
京都には、高校1年生から30歳までいました。 格さんとの出会いは大学生の時です。「あ、“たなばた”の人や!」って興奮したことを覚えています。それ以降、格さんの曲はたくさん演奏しています!でも実は「たなばた」は未だに演奏したことがないんですよね(笑)。
格さんとの出会いは大学生の時です。「あ、“たなばた”の人や!」って興奮したことを覚えています。それ以降、格さんの曲はたくさん演奏しています!でも実は「たなばた」は未だに演奏したことがないんですよね(笑)。 2025年、ラヴェルは生誕150周年、グレグソンは生誕80周年、そして我らが格さんは生誕55周年です(笑)。そして京都コンサートホールは30周年!そんなスペシャルアニバーサリーコンサートを開催しますので、沢山のお客さんに足を運んでいただけるようがんばります。京響ファンのみなさん!いつもとは違うメンバーの姿が見られますよ!ぜひ、お越しください。
2025年、ラヴェルは生誕150周年、グレグソンは生誕80周年、そして我らが格さんは生誕55周年です(笑)。そして京都コンサートホールは30周年!そんなスペシャルアニバーサリーコンサートを開催しますので、沢山のお客さんに足を運んでいただけるようがんばります。京響ファンのみなさん!いつもとは違うメンバーの姿が見られますよ!ぜひ、お越しください。 京都コンサートホールが誇る国内最大級のパイプオルガンをお楽しみいただける人気シリーズ「オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ」。11月1日に開催するVol.76にご出演いただく松居直美さんのインタビュー後編をお届けします。
京都コンサートホールが誇る国内最大級のパイプオルガンをお楽しみいただける人気シリーズ「オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ」。11月1日に開催するVol.76にご出演いただく松居直美さんのインタビュー後編をお届けします。
 J.S.バッハも初期から後期と作風は変化していて、若い時の作品は確かに若さを感じはしますが、作曲技法的に巧いなと思います。あまりに巧みであるし、あれだけのオルガン作品があっても曲の終わり方が全く同じ曲はないのです。たくさんの引き出しを持った人といいますか、バッハに至るまでの数々の音楽が吸収されていて、それがバッハの中で統合されて曲となって出てきていると思うのですが、1曲ずつの曲のキャラクターの違いの面白さもありますし、バッハ以上にどの作品を弾いても興味が持て、その興味が尽きることがない作曲家はいないように感じます。しばらく時間をおいて改めて演奏してみるとまた違った発見がいつもある作曲家は、バッハの他にはあまりいないような気がします。ですので、バッハの作品を理解したと思っているわけではありませんし、近づくほどに峰が高く見えるような、そんな存在です。
J.S.バッハも初期から後期と作風は変化していて、若い時の作品は確かに若さを感じはしますが、作曲技法的に巧いなと思います。あまりに巧みであるし、あれだけのオルガン作品があっても曲の終わり方が全く同じ曲はないのです。たくさんの引き出しを持った人といいますか、バッハに至るまでの数々の音楽が吸収されていて、それがバッハの中で統合されて曲となって出てきていると思うのですが、1曲ずつの曲のキャラクターの違いの面白さもありますし、バッハ以上にどの作品を弾いても興味が持て、その興味が尽きることがない作曲家はいないように感じます。しばらく時間をおいて改めて演奏してみるとまた違った発見がいつもある作曲家は、バッハの他にはあまりいないような気がします。ですので、バッハの作品を理解したと思っているわけではありませんし、近づくほどに峰が高く見えるような、そんな存在です。 オルガニストになるというビジョンは全くなかったですね。実は一度、オルガンを辞めようと思ったことがありました。大学院を卒業してから1年くらいの時期です。オルガン科を卒業しても “何かになれる” というモデルがあったわけではありませんし、可能性も考えられませんでした。私が学生の頃はオルガンのあるコンサートホールはなかったので、ホールオルガニストという職もありませんでした。しかし、その頃たまたま誘われて行った国際基督教大学でのコンサートを聴いて、 “もう一度オルガンを演奏したい” と思ったのです。そのコンサートで演奏していたのは、東ドイツのトーマス教会のオルガニストだったハンネス・ケストナーでした。
オルガニストになるというビジョンは全くなかったですね。実は一度、オルガンを辞めようと思ったことがありました。大学院を卒業してから1年くらいの時期です。オルガン科を卒業しても “何かになれる” というモデルがあったわけではありませんし、可能性も考えられませんでした。私が学生の頃はオルガンのあるコンサートホールはなかったので、ホールオルガニストという職もありませんでした。しかし、その頃たまたま誘われて行った国際基督教大学でのコンサートを聴いて、 “もう一度オルガンを演奏したい” と思ったのです。そのコンサートで演奏していたのは、東ドイツのトーマス教会のオルガニストだったハンネス・ケストナーでした。 20世紀を代表するフランスの偉大な音楽家 ピエール・ブーレーズの真髄に迫る、京都コンサートホールのオリジナル企画「ブーレーズへのオマージュ」。コンサートの翌日11月9日(日)には、ブーレーズの作品や思想への理解をさらに深めていただくため、京都市立芸術大学 堀場信吉記念ホールにてスペシャルイベント「ピアニスト永野英樹による公開マスタークラス」を開催します。
20世紀を代表するフランスの偉大な音楽家 ピエール・ブーレーズの真髄に迫る、京都コンサートホールのオリジナル企画「ブーレーズへのオマージュ」。コンサートの翌日11月9日(日)には、ブーレーズの作品や思想への理解をさらに深めていただくため、京都市立芸術大学 堀場信吉記念ホールにてスペシャルイベント「ピアニスト永野英樹による公開マスタークラス」を開催します。 ブーレーズに初めて会ったのはIRCAMでした。確か2009年です。私は2007年から2009年まで研究員として2年間、IRCAMに滞在していました。当時、修了作品を制作するため施設によく寝泊まりしていたのです。確か夜の22時頃だったと思うのですが、カフェで休憩しようと飲み物を取りにエレベーターを降りたら、ブーレーズが目の前にいたのです。僕は『え?』となりましたし、ブーレーズも『え?』となっていましたね(笑)。不思議な出会い方でした。その後、私の修了作品がポンピドゥー・センターでアンサンブル・アンテルコンタンポランの演奏により初演されることになったのですが、その時にもブーレーズは聴きに来ていました。作品を聴いていただいた後に直接お話ししたのですが、ものすごく緊張していて何をしゃべったかは覚えていません。でも『よかったよ』とは言ってもらえましたね。当時、ブーレーズはかなり高齢でしたので、一緒に活動をすることはなかったのですが、ブーレーズの存在感、そしてオーラのようなものを強く感じました。
ブーレーズに初めて会ったのはIRCAMでした。確か2009年です。私は2007年から2009年まで研究員として2年間、IRCAMに滞在していました。当時、修了作品を制作するため施設によく寝泊まりしていたのです。確か夜の22時頃だったと思うのですが、カフェで休憩しようと飲み物を取りにエレベーターを降りたら、ブーレーズが目の前にいたのです。僕は『え?』となりましたし、ブーレーズも『え?』となっていましたね(笑)。不思議な出会い方でした。その後、私の修了作品がポンピドゥー・センターでアンサンブル・アンテルコンタンポランの演奏により初演されることになったのですが、その時にもブーレーズは聴きに来ていました。作品を聴いていただいた後に直接お話ししたのですが、ものすごく緊張していて何をしゃべったかは覚えていません。でも『よかったよ』とは言ってもらえましたね。当時、ブーレーズはかなり高齢でしたので、一緒に活動をすることはなかったのですが、ブーレーズの存在感、そしてオーラのようなものを強く感じました。 パリに住んでいるときにブーレーズが指揮する姿を見たことがあります。作曲家としてのブーレーズと直接的な繋がりがあるかはわかりませんが、ブーレーズのリハーサルは極めて合理的なのですよね。楽譜を通してブーレーズの人柄を知ることは難しいと思うのですが、指揮者としてのブーレーズはきわめて厳格な音楽づくりをしていました。ただそれと同時に、ユーモアを忘れないという一面もあって、そういった場面に出会ったときに、『ああ、やっぱりブーレーズも人間なんだな』って思いました。僕が楽譜を通して知るブーレーズ以上に、指揮者ブーレーズは人間的だなと思います。楽譜からも論理だけでは片づけられない作曲家の顔みたいなものは見えるのですが、実際に指揮をしている姿を見ると結構インパクトがありました。
パリに住んでいるときにブーレーズが指揮する姿を見たことがあります。作曲家としてのブーレーズと直接的な繋がりがあるかはわかりませんが、ブーレーズのリハーサルは極めて合理的なのですよね。楽譜を通してブーレーズの人柄を知ることは難しいと思うのですが、指揮者としてのブーレーズはきわめて厳格な音楽づくりをしていました。ただそれと同時に、ユーモアを忘れないという一面もあって、そういった場面に出会ったときに、『ああ、やっぱりブーレーズも人間なんだな』って思いました。僕が楽譜を通して知るブーレーズ以上に、指揮者ブーレーズは人間的だなと思います。楽譜からも論理だけでは片づけられない作曲家の顔みたいなものは見えるのですが、実際に指揮をしている姿を見ると結構インパクトがありました。
 実は、この作品を演奏するのは今回が初めてです。作品のことはもちろん知っていましたし、重要なレパートリーであるということも分かっていましたが、これまで演奏する機会がありませんでした。《ドメーヌ》は、一時期親交のあったジョン・ケージの ”偶然性” の考え方から発展した “管理された偶然性” の作品です。 “管理された偶然性” というのは、ケージのように全てをコインやサイコロといった不確定なものに委ねるのではなく、全てが作曲家の意図のもとに統制されたうえで、奏者自身が演奏するフレーズの順番や奏法を選択しながら演奏するものです。
実は、この作品を演奏するのは今回が初めてです。作品のことはもちろん知っていましたし、重要なレパートリーであるということも分かっていましたが、これまで演奏する機会がありませんでした。《ドメーヌ》は、一時期親交のあったジョン・ケージの ”偶然性” の考え方から発展した “管理された偶然性” の作品です。 “管理された偶然性” というのは、ケージのように全てをコインやサイコロといった不確定なものに委ねるのではなく、全てが作曲家の意図のもとに統制されたうえで、奏者自身が演奏するフレーズの順番や奏法を選択しながら演奏するものです。 原曲が大編成の作品で、それをウェーベルンが五重奏に編曲しました。五重奏版では、原曲にある全ての音が入っているわけではありませんが、元の編成を踏襲した形でとてもよくできています。ピアノがたくさんのパートを担っているので音数も多く、どうしても響きが重厚で分厚くなってしますが、それに対し他の4つの楽器(フルート、クラリネット、ヴァイオリン、チェロ)がどうバランスをとっていくかが難しさの一つでもあります。また、指揮者がいれば問題なく合わせられるところも、5人の場合はアンサンブル力が試されます。大変ですがやりがいのある作品です。
原曲が大編成の作品で、それをウェーベルンが五重奏に編曲しました。五重奏版では、原曲にある全ての音が入っているわけではありませんが、元の編成を踏襲した形でとてもよくできています。ピアノがたくさんのパートを担っているので音数も多く、どうしても響きが重厚で分厚くなってしますが、それに対し他の4つの楽器(フルート、クラリネット、ヴァイオリン、チェロ)がどうバランスをとっていくかが難しさの一つでもあります。また、指揮者がいれば問題なく合わせられるところも、5人の場合はアンサンブル力が試されます。大変ですがやりがいのある作品です。



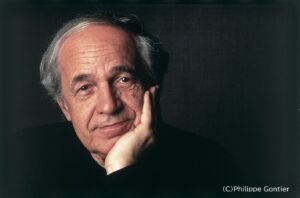
 毎年、名だたる指揮者と共に熱演を繰り広げてきた本フェスティバル。今年の指揮者はフェスティバル史上初となる海外の指揮者――オランダ出身の名匠
毎年、名だたる指揮者と共に熱演を繰り広げてきた本フェスティバル。今年の指揮者はフェスティバル史上初となる海外の指揮者――オランダ出身の名匠
 偉大なる2つの交響曲に挑む今年の「関西の音楽大学オーケストラ・フェスティバル」。
偉大なる2つの交響曲に挑む今年の「関西の音楽大学オーケストラ・フェスティバル」。