2025年12月、登録アーティストとして全21回のアウトリーチを終えた福田さんに、2年間の振り返りと、活動の集大成となる「最終年度リサイタル」について話を伺いましたので、前半・後半に分けてお届けします。
前半では、2年間のアウトリーチ活動について、語っていただきました。
――2 年間のアウトリーチ活動が終わりましたが、今の率直な気持ちを教えてください。
「楽しかった」の一言です。京都コンサートホールのアウトリーチ事業をきっかけに初めてアウトリーチというものに携わりました。はじめの研修で、アウトリーチについて座学で学んだものの、「本当にできるのだろうか・・・」と不安な気持ちで私の活動はスタートしました。でも、ホールのスタッフのみなさんとチームを組ませていただき、支えていただいたおかげで、心から楽しみながら活動できました。
――アウトリーチ活動を始める前、アウトリーチに対してどのような印象がありましたか。
研修時の様子 登録アーティストのオーディションを受けた時はアウトリーチの概要くらいしか知りませんでしたが、「楽しそう」という印象はありましたね。小学校や福祉施設に行き、ピアノを弾いて話をするといった、いわゆるトークコンサートのような、もう少し親しみやすいイメージを抱いていました。
オーディションの2次選考で、実際に小学4年生向けのプログラムを15分程実演するという課題があったのですが、今思い返すと、ピアノを弾いている時間がとても長く、話はしているものの一方的だったと思います。
研修を経て活動を重ねる中で、試行錯誤しながらプログラムを練り直したり、ホールのスタッフのみなさんや講師の方に相談しアドバイスをいただいたりしながら、いろいろな経験を積んで、やっと「私がやりたいアウトリーチってこういうものかな」というのが感覚的に分かるようになってきました。
――1 年前のインタビューで、アウトリーチを始めたきっかけは、故 福井尚子先生からの勧めだったと伺いました。(1 年前のインタビューはこちら をご覧ください。)
そうですね。ただ、もしかしたら「アウトリーチ活動をしてみたら」というよりは、「京都に貢献する演奏家になりたいのであれば、京都コンサートホールのアウトリーチ活動に参加してみては?」といった考えで勧めてくださったのかもしれないと、今は思っています。
第1期登録アーティストの募集チラシを見た時、「こんなことをするんだ」「楽しそうだな、やってみたいな」という気持ちはありましたが、当時は学生でしたのですぐに挑戦することはできませんでした。その後、大学院を卒業し2年間のフランス留学を終え帰国したタイミングで、第3期登録アーティストの募集がありました。しかも対象がピアノでしたので、タイミング的にも恵まれていましたね。私の中で「アウトリーチ活動をやってみたい」という気持ちが変わらずあったので、オーディションを受けました。
――2 年間のアウトリーチ活動で思い出に残っていること・印象深かったことを教えてください。
でも、アウトリーチで出会った子どもたちは、大人もびっくりするくらいの想像力を持っていました。ただ単に音楽を聴くだけでなく、聴いた音楽から作曲家の想いや情景を想像できる力です。しかもそれは感覚的なものだけでなく、「始めと終わりに同じ旋律が出てきた」「音がだんだん大きくなっていた」「音が下がっていったから悲しい感じがした」など、いわゆる楽曲分析的なことを自然にしながら聴いていたんですね。そのように楽しみながら音楽を聴いてほしいと思っていましたので、このような場面に出会えた時は嬉しかったです。
――アウトリーチ活動の中で、常に意識していたことはありますか。
話をする際、常に聴き手の表情を見るように心がけました。また、必ず目を合わせ、自分に話しかけてもらっていると感じてもらえるよう意識しました。
――確かに、福田さんは子どもたちと話をするときに、子どもたちの輪の中に入っていって、姿勢を低くして話しかけていましたね。
何も考えずに自然とそうなっていましたね。初回のアウトリーチの時、相手が小さいので見下ろす形だと話しづらいのではないかと思い、しゃがんで私から見上げる形にしてみたら、スタッフさんから「すごい良かった!」と言ってもらえて。私自身もその方がコミュニケーションがとりやすかったので、それからは常にそうやってコミュニケーションを取るようにしました。
――プログラムで工夫した点・意識した点はありますか。
私がアウトリーチを行ったのは小学校が多かったため、参加型のアクティビティ(一緒に歌ったり、身体を動かしたり、クイズなど)をいくつかプログラムに取り入れました。私の演奏と話を聴いてもらうという一方通行のコミュニケーションではなく、一緒に楽しむアトラクションのようなイメージを持つようにしました。「一緒に」「参加しながら」「みんなで」といったことをいつも意識していましたね。
――福田さんがアウトリーチで一番伝えたかったことは何ですか。
「自分の経験と音楽を重ね合わせて、音楽を楽しんでほしい」ということです。これは1年目から変わっていません。日頃クラシック音楽に馴染みのない方にとっては、クラシック音楽=堅苦しいという印象がどうしてもあるかと思います。そのような中で、少しでも「クラシック音楽っていいな」「もっと聴いてみたいな」と思っていただくには、自分の経験と重ねながら聴いていただくことが一番だと考えました。少しだけ曲の背景や作曲家について説明をしつつ、あとは自由に想像しながら聴いてもらう。そこで何か、自分の経験や気持ちと重なる「共感」があれば、クラシック音楽を好きになってもらえると思っています。
――福田さんは活動1 年目と2 年目でプログラムの構成は変えていませんね。前半は視覚的・身体的に音楽を楽しみ、後半は音楽を聴いて情景や気持ちを想像する。伝えたいことが明確だったからだと思いますが、このプログラムに至った経緯を教えてください。
最初の研修で、講師の児玉真先生から「アウトリーチは聴き手のためにするもの。アウトリーチを通して、音楽が聴き手の心を豊かにしたり何らかの人生の助けになったりする。その一方で、演奏家にとっても何かメリットがなければいけない。一方的な奉仕ではなく、Win-Winの形であることが望ましい。そう考えたとき、あなたがアウトリーチで伝えたいことは何ですか」と問われました。
当時の私にとっては結構斬新というか、ハッとさせられました。綺麗ごとかもしれませんが、私がピアニストとして演奏するとき、「お客様に楽しんでいただきたい、聴いてよかったなと感じていただける演奏会にしたい」と思っていますが、演奏家にとってのメリットについては、少なくとも私自身は考えたことがありませんでした。
私にとってのメリットは何だろう…と考えたとき、一番に思い浮かんだことは、私の演奏をきっかけに「聴き手に音楽を好きになってもらえること」「聴き手の人生において、音楽が何かしらの役に立つこと」でした。そして「Join us!~キョウト・ミュージック・アウトリーチ」は京都コンサートホールの事業ですので、ホールの想い・目的も大切にしたいと思いました。この事業の目的は「さまざまな理由でホールに来館できない方、クラシック音楽に接する機会の少ない方などに、クラシック音楽の喜びや楽しさを生演奏として届ける」ことです。その点においては、私の想いとホールの想いは一致していましたので、「 “クラシック音楽は面白いものだよ” と感じていただけるプログラムを組み立てよう!」となりました。
プログラムを組み立てるうえで、一緒に歌ったり身体を動かしたり、クイズを用いて知識を増やしていくことが楽しいのはもちろんですが、それを超えて「音楽を聴いて自由に想像する楽しさ」まで到達してもらいたいと思いました。ですので、まずは親しみのある曲でピアノとの距離を縮め、リズミカルな音楽を使って身体で音楽を体感してもらいつつ、最後は音楽で描かれた情景や作曲家の気持ちを想像するといった、徐々に内面にアプローチしていけるようなプログラム構成にしました。
――活動の中で、京都コンサートホールの登録アーティストでよかったと感じることはありましたか。
2025年3月ジョイントコンサートの様子 まず、ホールのスタッフのみなさんのサポートがとても心強かったです。ピアニストはどうしても1人で活動することが多いですが、常に支えてくださりチームとして活動している感覚でした。また年1回、1年目のジョイント・リサイタル、そして2年目の最終年度リサイタルと、ホールでの演奏機会をいただけることは、ピアニストとして大変貴重です。私自身、小さなころからコンクールや高校の定期演奏会など、何度も京都コンサートホールの舞台立っていますが、どれも思い出深い、そして私にとってはターニングポイントとなるような本番ばかりですね。
そして何よりも嬉しいのは、アウトリーチで京都の子どもたちに会えること、京都の施設で演奏できることです。自分の出身地で音楽活動ができることは音楽家として何よりの幸せですし、登録アーティストであるからこそできることでもあります。アウトリーチのたびに、京都コンサートホールの登録アーティストに選んでいただけてよかったと感じています。
――アウトリーチを終えて、福田さんが得たものを教えてください。
アウトリーチ先の学校にて 演奏家として宝物のような経験をたくさん積ませていただきました。また、留学を終えてこれからピアニストとして歩んでいくうえで何を伝えたいのか、自分自身と向き合う時間ともなりました。
音楽を通じてたくさんの方に出会い、思いを通わせ合うことができました。一般的なコンサートではアウトリーチのような距離感でお客様とコミュニケーションを取ることは難しいです。もちろんコンサートでも言葉(お話)がないだけで、その瞬間に聴き手が感じていることが言葉にならずとも発せられていると感じてはいましたが、そういったことをアウトリーチを通してはっきりと実感することができました。アウトリーチを経験しなければ得られなかったものであり、何よりそれがアウトリーチの楽しさでもありました。
――ありがとうございました。あっという間の2 年間でしたが、とても充実した2 年間でしたね。後半では、活動の集大成となる「最終年度リサイタル」について話を伺いました。後半もどうぞお楽しみに!
(2025年12月 京都コンサートホール事業企画課インタビュー)
♪3月7日(土)開催「最終年度リサイタル Vol.1 福田優花 ピアノ・リサイタル」の詳細はこちら!
 そうなんです。アウトリーチ公演のなかで、私がピアノを大好きになったきっかけのひとつとして、ショパン100選のCDを紹介していました。CDは小学生の頃に両親からプレゼントしてもらったものなのですが、傷だらけになるくらい何度も何度も聴いてきました。そのCDのなかには、今回のリサイタルのメインである、ショパンのソナタ第3番が入っており、小さい頃から「いつか弾きたい!」とずっと憧れてきました。全楽章演奏するのは今回が初めてですので、この機会に演奏できることが非常に嬉しいです。
そうなんです。アウトリーチ公演のなかで、私がピアノを大好きになったきっかけのひとつとして、ショパン100選のCDを紹介していました。CDは小学生の頃に両親からプレゼントしてもらったものなのですが、傷だらけになるくらい何度も何度も聴いてきました。そのCDのなかには、今回のリサイタルのメインである、ショパンのソナタ第3番が入っており、小さい頃から「いつか弾きたい!」とずっと憧れてきました。全楽章演奏するのは今回が初めてですので、この機会に演奏できることが非常に嬉しいです。 シューベルト、シューマン、フォーレ、ドビュッシー。今回のプログラムで取り上げている作曲家全員、ピアノ作品の中に詩情を入れて作曲している作曲家だと思います。そういった作曲家の作品を並べて、そこに描かれている詩情を、ピアノで私なりに解釈したいと思い、このテーマで選曲しました。
シューベルト、シューマン、フォーレ、ドビュッシー。今回のプログラムで取り上げている作曲家全員、ピアノ作品の中に詩情を入れて作曲している作曲家だと思います。そういった作曲家の作品を並べて、そこに描かれている詩情を、ピアノで私なりに解釈したいと思い、このテーマで選曲しました。 スタッフ①(山田)まずは2年間、お疲れ様でした。本当に努力家で、ひとつひとつのことに丁寧に取り組みながら、たくさんの素敵なアウトリーチ公演を京都市内でお届けしてくださりありがとうございました。ご本人のお話のなかで、宮國さんご自身の変化として、前向きに物事を捉えることができるようになったとおっしゃっていましたが、それはそばで見ている私たちも感じていました。この2年間でピアニストとしてもそれ以外の面でも、本当にたくましくご成長される姿を間近で見守らせていただけて、私たちも嬉しかったです!
スタッフ①(山田)まずは2年間、お疲れ様でした。本当に努力家で、ひとつひとつのことに丁寧に取り組みながら、たくさんの素敵なアウトリーチ公演を京都市内でお届けしてくださりありがとうございました。ご本人のお話のなかで、宮國さんご自身の変化として、前向きに物事を捉えることができるようになったとおっしゃっていましたが、それはそばで見ている私たちも感じていました。この2年間でピアニストとしてもそれ以外の面でも、本当にたくましくご成長される姿を間近で見守らせていただけて、私たちも嬉しかったです! スタッフ②(高野)この2年間を通して、初めは見えていなかった宮國さんのお茶目な部分が徐々に見え出して、真面目なだけでなく実は面白い人なのかなって感じました。ですので、この2年間のアウトリーチ活動の中で、宮國さんの持っていらっしゃる魅力的な部分を皆さんにお伝えすることができたことがとても良かったなと思います。子どもたちとの距離も公演を重ねるごとにどんどん縮まっていったことも見ていて嬉しかったです。
スタッフ②(高野)この2年間を通して、初めは見えていなかった宮國さんのお茶目な部分が徐々に見え出して、真面目なだけでなく実は面白い人なのかなって感じました。ですので、この2年間のアウトリーチ活動の中で、宮國さんの持っていらっしゃる魅力的な部分を皆さんにお伝えすることができたことがとても良かったなと思います。子どもたちとの距離も公演を重ねるごとにどんどん縮まっていったことも見ていて嬉しかったです。





 心に響く音楽を皆さんに届けたいです。
心に響く音楽を皆さんに届けたいです。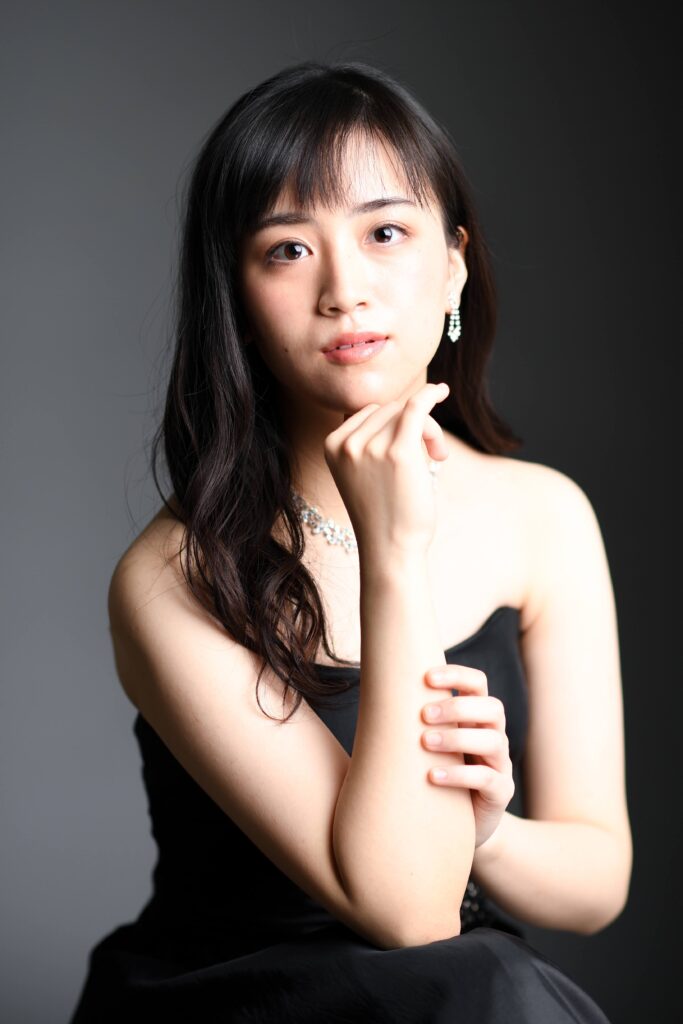 2024年度から2年間、京都コンサートホール第3期登録アーティストとして活動してきた、ピアニストの福田優花さん。後半では登録アーティストとしての活動の集大成となる「最終年度リサイタル」について話を伺いました。
2024年度から2年間、京都コンサートホール第3期登録アーティストとして活動してきた、ピアニストの福田優花さん。後半では登録アーティストとしての活動の集大成となる「最終年度リサイタル」について話を伺いました。 はじめに演奏するドビュッシーの《亜麻色の髪の乙女》は、みなさんよくご存じの曲だと思いますが、原曲は片思いを表現した詩をもとに作られた歌曲で、後にピアノ独奏用に編曲されました。
はじめに演奏するドビュッシーの《亜麻色の髪の乙女》は、みなさんよくご存じの曲だと思いますが、原曲は片思いを表現した詩をもとに作られた歌曲で、後にピアノ独奏用に編曲されました。 何かひとつでも聴き手の気持ち・経験と重なればと思い、様々な愛に繋がる作品を選曲しました。また、冒頭に演奏する《亜麻色の髪の乙女》はよく知られた曲ですので、「これから2時間のコンサートが始まる…」という緊張感をほぐすという意味で、リラックスしてお聴きいただけるのではないかと思い、1曲目に選びました。また、ヒナステラの作品は他の曲と比べて、雰囲気・曲調がガラッと変わります。アウトリーチの時も感じたのですが、身体を使った曲やリズミカルな曲は人の本能に響きます。楽しい気持ちになっていただき、前半を終えたいとの狙いでプログラミングしました。
何かひとつでも聴き手の気持ち・経験と重なればと思い、様々な愛に繋がる作品を選曲しました。また、冒頭に演奏する《亜麻色の髪の乙女》はよく知られた曲ですので、「これから2時間のコンサートが始まる…」という緊張感をほぐすという意味で、リラックスしてお聴きいただけるのではないかと思い、1曲目に選びました。また、ヒナステラの作品は他の曲と比べて、雰囲気・曲調がガラッと変わります。アウトリーチの時も感じたのですが、身体を使った曲やリズミカルな曲は人の本能に響きます。楽しい気持ちになっていただき、前半を終えたいとの狙いでプログラミングしました。
 まだまだ演奏家としては未熟ですので、様々なことにチャレンジしていきたいと思っていますし、アウトリーチ活動もできる限り続けていきたいです。具体的には、アウトリーチのように聴き手と密にコミュニケーションが取れるようなコンサートをしてみたいです。大きなホールで演奏できるのはとても嬉しいのですが、聴き手のみなさんの表情が見えるくらいのサロンのような空間でお客さんと言葉を交わし、感じたことを共有しながら創り上げていくコンサートができたら素敵だなと思うようになりました。
まだまだ演奏家としては未熟ですので、様々なことにチャレンジしていきたいと思っていますし、アウトリーチ活動もできる限り続けていきたいです。具体的には、アウトリーチのように聴き手と密にコミュニケーションが取れるようなコンサートをしてみたいです。大きなホールで演奏できるのはとても嬉しいのですが、聴き手のみなさんの表情が見えるくらいのサロンのような空間でお客さんと言葉を交わし、感じたことを共有しながら創り上げていくコンサートができたら素敵だなと思うようになりました。

 2024年度から2年間、京都コンサートホール第3期登録アーティストとして活動してきた、ピアニストの福田優花さん。2024年度は市内の小学校、2年目となる2025年度は小学校に加え、幼稚園や支援施設にも伺い、クラシック音楽を届けてきました。
2024年度から2年間、京都コンサートホール第3期登録アーティストとして活動してきた、ピアニストの福田優花さん。2024年度は市内の小学校、2年目となる2025年度は小学校に加え、幼稚園や支援施設にも伺い、クラシック音楽を届けてきました。
 初めはとにかく、曲のこと・ピアノのことをいろいろ説明していました。クラシック音楽に慣れ親しんでいる人であれば、曲名を聞いていろいろ想像できるかもしれませんが、日ごろクラシック音楽を聴かない方の場合は、説明がないと分かりづらいだろうと勝手に思い込んでいたのです。
初めはとにかく、曲のこと・ピアノのことをいろいろ説明していました。クラシック音楽に慣れ親しんでいる人であれば、曲名を聞いていろいろ想像できるかもしれませんが、日ごろクラシック音楽を聴かない方の場合は、説明がないと分かりづらいだろうと勝手に思い込んでいたのです。











 たちによる夢の競演「ブラス・スターズ in KYOTO」(11月30日)。
たちによる夢の競演「ブラス・スターズ in KYOTO」(11月30日)。 初めて作曲をしたのは、たしかピアノを初めてすぐの頃でした。ピアノ曲で、「子犬の行進」や「星のうた」といったタイトルをつけて作曲していました。幼い頃から「楽譜を書く」ことが何より好きだったみたいです。
初めて作曲をしたのは、たしかピアノを初めてすぐの頃でした。ピアノ曲で、「子犬の行進」や「星のうた」といったタイトルをつけて作曲していました。幼い頃から「楽譜を書く」ことが何より好きだったみたいです。 実は「たなばた」の作曲は高校時代にしました。私の曲には転調が繰り返し現れるので、当時高校の同級生には難しいと感じられて、よく煙たがられていましたね(笑)。だから、「たなばた」も当時演奏されることはあまりありませんでした・・・。「たなばた」が日の目を見ることになったのは大阪音楽大学2年生の時です。当時大学で吹奏楽を指導していらっしゃった先生たちの前で「たなばた」をピアノで初披露したところ気に入ってくださり、そのまま吹奏楽編成で演奏していただきました。
実は「たなばた」の作曲は高校時代にしました。私の曲には転調が繰り返し現れるので、当時高校の同級生には難しいと感じられて、よく煙たがられていましたね(笑)。だから、「たなばた」も当時演奏されることはあまりありませんでした・・・。「たなばた」が日の目を見ることになったのは大阪音楽大学2年生の時です。当時大学で吹奏楽を指導していらっしゃった先生たちの前で「たなばた」をピアノで初披露したところ気に入ってくださり、そのまま吹奏楽編成で演奏していただきました。 ラヴェルの「道化師の朝の歌」についてはとても難しい楽曲ですが、ピアノと打楽器が入ることによって色々な工夫ができるので、それがとても楽しいです。「800秒間世界一周」についてはお気づきの方もいらっしゃると思いますが、1956年にアメリカで公開された映画「80日間世界一周」にかけています。この曲では、まず日本を出発し、色んな世界の音楽を聴いてもらいながら、お客さんに世界旅行の気分を味わってもらいたいなと思っています。それぞれの楽器にフィーチャーして、色んな表現をお客様にお聴きいただけたらいいなと思っています。
ラヴェルの「道化師の朝の歌」についてはとても難しい楽曲ですが、ピアノと打楽器が入ることによって色々な工夫ができるので、それがとても楽しいです。「800秒間世界一周」についてはお気づきの方もいらっしゃると思いますが、1956年にアメリカで公開された映画「80日間世界一周」にかけています。この曲では、まず日本を出発し、色んな世界の音楽を聴いてもらいながら、お客さんに世界旅行の気分を味わってもらいたいなと思っています。それぞれの楽器にフィーチャーして、色んな表現をお客様にお聴きいただけたらいいなと思っています。
 京都には、高校1年生から30歳までいました。
京都には、高校1年生から30歳までいました。 格さんとの出会いは大学生の時です。「あ、“たなばた”の人や!」って興奮したことを覚えています。それ以降、格さんの曲はたくさん演奏しています!でも実は「たなばた」は未だに演奏したことがないんですよね(笑)。
格さんとの出会いは大学生の時です。「あ、“たなばた”の人や!」って興奮したことを覚えています。それ以降、格さんの曲はたくさん演奏しています!でも実は「たなばた」は未だに演奏したことがないんですよね(笑)。 2025年、ラヴェルは生誕150周年、グレグソンは生誕80周年、そして我らが格さんは生誕55周年です(笑)。そして京都コンサートホールは30周年!そんなスペシャルアニバーサリーコンサートを開催しますので、沢山のお客さんに足を運んでいただけるようがんばります。京響ファンのみなさん!いつもとは違うメンバーの姿が見られますよ!ぜひ、お越しください。
2025年、ラヴェルは生誕150周年、グレグソンは生誕80周年、そして我らが格さんは生誕55周年です(笑)。そして京都コンサートホールは30周年!そんなスペシャルアニバーサリーコンサートを開催しますので、沢山のお客さんに足を運んでいただけるようがんばります。京響ファンのみなさん!いつもとは違うメンバーの姿が見られますよ!ぜひ、お越しください。 京都コンサートホールが誇る国内最大級のパイプオルガンをお楽しみいただける人気シリーズ「オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ」。11月1日に開催するVol.76にご出演いただく松居直美さんのインタビュー後編をお届けします。
京都コンサートホールが誇る国内最大級のパイプオルガンをお楽しみいただける人気シリーズ「オムロン パイプオルガン コンサートシリーズ」。11月1日に開催するVol.76にご出演いただく松居直美さんのインタビュー後編をお届けします。
 J.S.バッハも初期から後期と作風は変化していて、若い時の作品は確かに若さを感じはしますが、作曲技法的に巧いなと思います。あまりに巧みであるし、あれだけのオルガン作品があっても曲の終わり方が全く同じ曲はないのです。たくさんの引き出しを持った人といいますか、バッハに至るまでの数々の音楽が吸収されていて、それがバッハの中で統合されて曲となって出てきていると思うのですが、1曲ずつの曲のキャラクターの違いの面白さもありますし、バッハ以上にどの作品を弾いても興味が持て、その興味が尽きることがない作曲家はいないように感じます。しばらく時間をおいて改めて演奏してみるとまた違った発見がいつもある作曲家は、バッハの他にはあまりいないような気がします。ですので、バッハの作品を理解したと思っているわけではありませんし、近づくほどに峰が高く見えるような、そんな存在です。
J.S.バッハも初期から後期と作風は変化していて、若い時の作品は確かに若さを感じはしますが、作曲技法的に巧いなと思います。あまりに巧みであるし、あれだけのオルガン作品があっても曲の終わり方が全く同じ曲はないのです。たくさんの引き出しを持った人といいますか、バッハに至るまでの数々の音楽が吸収されていて、それがバッハの中で統合されて曲となって出てきていると思うのですが、1曲ずつの曲のキャラクターの違いの面白さもありますし、バッハ以上にどの作品を弾いても興味が持て、その興味が尽きることがない作曲家はいないように感じます。しばらく時間をおいて改めて演奏してみるとまた違った発見がいつもある作曲家は、バッハの他にはあまりいないような気がします。ですので、バッハの作品を理解したと思っているわけではありませんし、近づくほどに峰が高く見えるような、そんな存在です。 オルガニストになるというビジョンは全くなかったですね。実は一度、オルガンを辞めようと思ったことがありました。大学院を卒業してから1年くらいの時期です。オルガン科を卒業しても “何かになれる” というモデルがあったわけではありませんし、可能性も考えられませんでした。私が学生の頃はオルガンのあるコンサートホールはなかったので、ホールオルガニストという職もありませんでした。しかし、その頃たまたま誘われて行った国際基督教大学でのコンサートを聴いて、 “もう一度オルガンを演奏したい” と思ったのです。そのコンサートで演奏していたのは、東ドイツのトーマス教会のオルガニストだったハンネス・ケストナーでした。
オルガニストになるというビジョンは全くなかったですね。実は一度、オルガンを辞めようと思ったことがありました。大学院を卒業してから1年くらいの時期です。オルガン科を卒業しても “何かになれる” というモデルがあったわけではありませんし、可能性も考えられませんでした。私が学生の頃はオルガンのあるコンサートホールはなかったので、ホールオルガニストという職もありませんでした。しかし、その頃たまたま誘われて行った国際基督教大学でのコンサートを聴いて、 “もう一度オルガンを演奏したい” と思ったのです。そのコンサートで演奏していたのは、東ドイツのトーマス教会のオルガニストだったハンネス・ケストナーでした。