長年フランスに在住し、いまは亡きピエール・ブーレーズ率いる現代音楽のエキスパート集団「アンサンブル・アンテルコンタンポラン」の専属ピアニストとして、世界の第一線で活躍し続けてきた永野英樹氏。
永野英樹©J.RADEL ――永野さんはフランス在住でいらっしゃいますが、いつから住んでいらしゃるのですか?
永野英樹 (以下、敬称略):88年の夏ですね。今年の8月でちょうど30年になります。
――フランスではどういった活動をされているのでしょうか?
永野 :僕は96年から「アンサンブル・アンテルコンタンポラン」というグループで活動しているんですが、その仕事が90%を占めています。
――現代音楽のエキスパート集団「アンサンブル・アンテルコンタンポラン」ですが、どのようなグループか教えてくださいますか。
永野 :1976年、ピエール・ブーレーズ (1925-2016) はその当時フランスの首相だったジョルジュ・ポンピドゥーから、IRCAM(電子音楽や音響に関して探求する研究所)の創設に関わる責任者になるよう命じられたんです。
このアンサンブルは確かにブーレーズが創設に関わったんですけど、別に彼の曲ばかりをやるというわけではなく、「20世紀以降の作品を広めましょう、初演もしましょう」というスタンスで活動しています。もちろん、20世紀のクラシック古典もしますよ。
――どのようにして「アンサンブル・アンテルコンタンポラン」に入団したのですか?
永野 :ここは毎回、オーディションがあるんですよ。それがたまたまショパンコンクールの年(1995年)と重なってしまったんです。
アンサンブル・アンテルコンタンポランにはピアノのポストが3つあったのですが、当時在籍していたピエール=ロラン・エマールがおやめになるということで、ちょうどその時ポストが1つ空いたのです。
――凄いピアニストが在籍していたのですね。
永野 :まぁ、そういうところではあるんですけど。
――「アンサンブル・アンテルコンタンポラン」のオーディションではなにを演奏されたのですか?
永野 :オーディションは、半分クラシックな感じでした。ベートーヴェンの「熱情ソナタ」1楽章、ドビュッシー前奏曲集から1曲、シェーンベルクの作品(作品33b)、それにブーレーズのソナタ3番の1楽章から抜粋、あとは自由に弾いて良いと言われたので、僕はその直前に弾いていたリゲティのエチュードを演奏しました。それで、ファイナルの審査では初見の審査がありました。
――きついですね、ショパンコンクールの直後ですもんね。
永野 :はい、きつかったです。全然準備できてなくて。本当に間際ですよね。
ショパンコンクールがあまりうまくいかなかったんです。すごい長い時間かけて準備してきたものが終わった後、気が抜けちゃって。すぐ次の課題に取り掛かれなくて・・・。ちょっとボーっとした期間がありました。でも「そろそろやるか」って腰を上げたのがオーディションの1週間前!譜読みはすでにしていましたが、ちゃんと練習したのは1週間前でしたね。
――・・・すごく濃い1週間でしたね。
永野 :そうなんです。それこそダメ元で受けましたよ。
ですが、いまでは笑い話ですけど、ブーレーズのが病院に行かないといけないという理由で、僕、その日の8時に弾かされたんですよ。
――え?8時って朝?!
永野 :そう、朝!(笑)いまだに忘れられないですよね。7時30分とかに会場行って、30分くらい指ならししました。あの日、ブーレーズは10時に病院へ行かなくてはいかなかったんですよね。1人1時間の演奏で2人だから、8時スタート(笑)。
――朝8時の本番って、あまりないですよね・・・
永野 :そうでしょう。しかもですね、前日の夜の8時過ぎに電話で「オーディションに通りました」っていう連絡をもらったんです。それでこう続けるわけです、「明朝8時に弾きに来てくださいね」って(笑)。結果合格しましたが、すごいオーディションでしたよ。一生忘れられませんね。
――本当に、一生の思い出ですよね(笑)。
永野 :そうなんです。最初はけっこう辛かったですね。毎回、これまで演奏したことのない曲を演奏しなければならなかったのです。最初の3年間は少し辛かったですね。当時はかなりストレスというか、反動的にクラシックやりたくてたまらなかったです。
©Kyoto Concert Hall ――永野さんはもともとどの作曲家がお好きだったんですか。
永野 :そうですねぇ・・・。ショパン・コンクールを受けるくらいだからもちろんショパンは嫌いではなかったですし、モーツァルトも好きでしたね。
もともと、僕がピアノを始めるきっかけはドビュッシーにあったんです。
――ドビュッシーにとってラヴェルはやはり比較対象でしょうか。
永野 :そうですねぇ。僕はフランスものが持つカラーが好きなんですけど、ラヴェルっていうのはどちらかというと、「知」に刺激を受けるようなものがあると思うんです。
でもドビュッシーって逆に、「情」の方じゃないですか。
もう亡くなってしまわれたのですが、むかし東京藝大に伊達純先生っていう先生がいらっしゃったんです。僕の師匠なんですが、フランスから一時帰国したときにそういう話をしたことがあります。
――ドビュッシーの作品の中で特に好きなものやよく演奏する作品ってありますか?
永野 :実は僕、ドビュッシーの持ち曲って少ないんですけど、やっぱり後期の作品は素晴らしいですよね。
そういう目で見ると、ドビュッシーの方がぐんと先に、作曲法としてはもう現代に近づいていたことをしていたんですよね。後期の作品は斬新だし、素晴らしい品格を持ったものが多いです。
©Kyoto Concert Hall ――今回、永野さんが演奏してくださるプログラムにはフォーレ・ラヴェル・ドビュッシーの歌曲が入っていますね。
永野 :選曲はサロメ・アレールさんと相談しながら決めたんですけど、最終的にわりとこう、有名所の3人が並んでしまう形になって、それはそれで面白いかなって思っています。
今回プログラミングされた作品はすべて、フランス音楽に馴染みない方にでもすっと入りやすいような曲だと思っています。
――ところで今回共演なさるサロメ・アレールさんはどのような歌手でいらっしゃいますか?
サロメ・アレール 永野 :彼女とのファーストコンタクトは、何年前になるのかなぁ・・・。
最初のコンサートをやったときに経歴を見たんですけど、もともと現代音楽専門家ではなくて、むしろバロック専門の方なんですよね。バロックと現代音楽。すごいですよね。
――たぶん、このコンサートでフランス歌曲を初めて生で聞くという方もいっぱいいらっしゃると思います。そういった方々にもフランス歌曲の魅力をお伝え出来れば良いですよね。
永野 :僕が出演する第2回「ベル・エポック」には、さまざまな楽曲がプログラミングされています。歌だけではなく、室内楽もありますよね。
僕自身はフランス歌曲がとても好きですし、歌い手はフランスの方で、素晴らしい歌手です。とても良いコンディションで皆様に聴いていただけると思います。
――素敵なお話をたくさんありがとうございました!
(京都コンサートホール事業企画課インタビュー@国立西洋美術館/2018年7月16日)
⇒【特別連載①】ドビュッシーとパン(牧神) ⇒【特別連載②】進々堂 続木社長インタビュー(前編) 【特別連載③】進々堂 続木社長インタビュー(後編) 【特別連載⑤】ハーピスト 福井麻衣に迫る<その1> スペシャル・シリーズ《光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー》の特設ぺージはこちら。
Hikaru.☆-300x200.jpg)









c伊藤菜々子-1024x683.jpg)
-724x1024.jpg)



-724x1024.jpg)


small-725x1024.jpg)








-e1541146463987-1024x794.jpg)


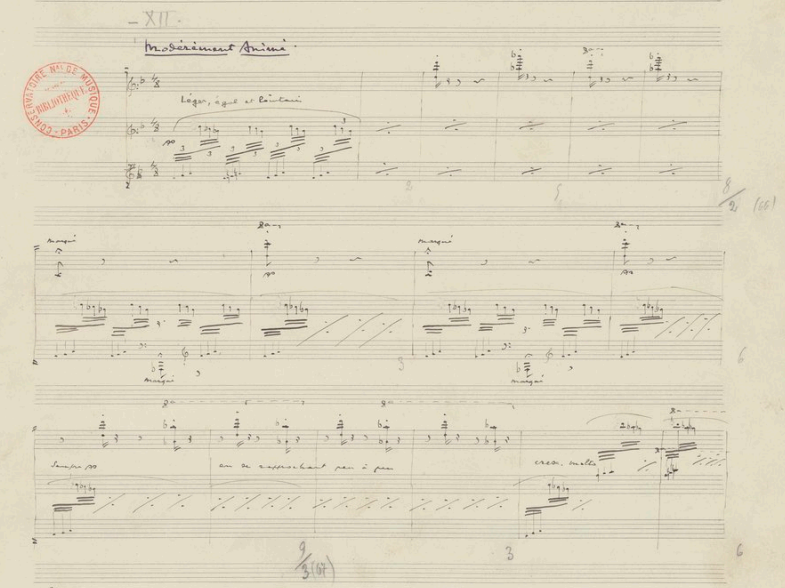

-1024x683.jpg)





 去年、ブロムシュテットの90歳のお誕生日を祝う公演がありました。彼は年々若返っていくように感じます。お誕生日翌日からリハーサルが始まりまして、NDRからサプライズでケーキと、ソロトロンボーン奏者のシモーネがアレンジしたスウェーデン民謡(?)の演奏をプレゼントしました。ブロムシュテットが子ども時代、夏休み前に歌っていた曲だったそうで、演奏を聴いて涙を流す様子に、わたしたちもジーンときました。
去年、ブロムシュテットの90歳のお誕生日を祝う公演がありました。彼は年々若返っていくように感じます。お誕生日翌日からリハーサルが始まりまして、NDRからサプライズでケーキと、ソロトロンボーン奏者のシモーネがアレンジしたスウェーデン民謡(?)の演奏をプレゼントしました。ブロムシュテットが子ども時代、夏休み前に歌っていた曲だったそうで、演奏を聴いて涙を流す様子に、わたしたちもジーンときました。













